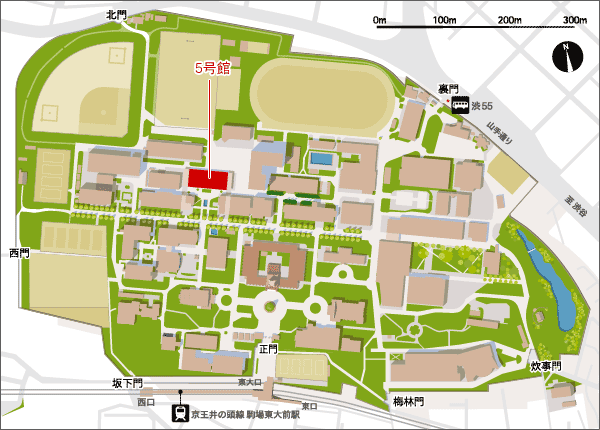|
2012.10.12 於日本女子大学目白キャンパス
ワークショップ「科学技術文明史と倫理」
(「日本倫理学会2012年度大会」内企画)
☆★このワークショップはどなたでもご参加できます(申込み不要)★☆
〇 趣旨文
科学技術文明社会という言い方がある。科学技術と社会政治文化が相補相乗的に形成するシステムの在り様を示す。このシステムは、石炭から石油、そして原子力に至るエネルギー所有の変遷と共にあるが、その一大特徴としては「最終目的がない」ことが挙げられるかもしれない。レイチェル・カーソンは、このことを踏み車にたとえ、一度踏み始めると止めたらどうなるかこわくて止められないと指摘した。
踏み車を踏み続けざるをえない現代の私たちは、その受動性ゆえに、自らを「第三者」と見なそうとする。強いて言えば「良心の立入禁止区域」(ギュンター・アンデルス)を設けようとする。だが、その「立入禁止区域」は今、少しずつ浸食される状態にあるのかもしれない。やましさや居心地悪さが強まり、「第三者はない」(宇井純)のだと、私たちを疼かせ始めてはいないか。
私たちの陥るこの「自縛装置」(十川治江)は、そうであれば尚のこと、そこに踏み込む必要がある。今回は、この科学技術文明史自体を解きほぐし、その表の歴史からは消えた可能性をも訊ねたい。私たち自身がかつて持った生命(いのち)観、有機体論のもつ可能性、そしてシモーヌ・ヴェイユの「脱創造」、進歩史観以前の中世哲学などから示唆を得たい。
〇 参加者 (敬称略)NEW:
最首悟 (いのち論)
黒住真 (【司会】日本思想史・倫理学・比較思想宗教)
今村純子 (思想史・映像倫理学)
丹波博紀 (思想史・人類学)
〇 参加者による提題:
【提題1】 〈ゾーン〉(立入禁止区域)としての科学技術文明社会
ゾーン――人によって立入を禁止された区域を指してそう呼ぶことがある。たとえばタルコフスキーの映画「ストーカー」(一九七九年)では劇中に登場する謎の空間がそう呼ばれている。ここでは現代社会を、無数のゾーンが折り重なり形成されていると捉えてみたい。
ゾーンが立入禁止なのは、直截にはゾーンの外部の人や物事に対してである。一方、ゾーンの内部にいる者は波風を極力立てず、感情の振幅を穏やかにし、ゾーンの存在は疑わぬことが重要である。私たちはそのようにして研究や趣味、運動、家庭等々、二重三重のゾーンを器用に使い分けながら生活している。
もちろん、ゾーンに対する批判がないわけではない。たとえば滝沢克己はそれを「疑似普遍性」と痛罵し、脚下の「本当の根《radix》」に気づけと説いた。だが、そもそも自らが(「根」に気づけない)根なし草で、糸の切れた凧ならば、ゾーンで生きる以外に到底やりようがないのだ。
こうしたゾーンと、科学はどう関係するのだろう。なぜならば現代社会は科学と切り離せず、「社会の科学的技術的複雑性を高めることに科学自身が寄与することによって、同時に科学は社会をさらにいっそう強く広く科学に依存せしめる」(G・ベーメほか「科学の目的内在化」)のだから。
科学はクリアカットな論理体系を欲する営みである。科学者はその論理体系を土台にして誤差の少ない想定を立てようとする。そしてその想定は、今日あらゆる領域に適用され、「社会的現実を、勝手に作りあげ、それにことばを与える力」(イリイチ)ともなっている。ベーメたちによれば、こうした科学の役割の増大化は一九世紀以降、特に顕著になった。
だがその一方で、「想定」を立てる科学者自身は、当然いくつものゾーンを行き来して生活している。ならば、大学の研究室等での科学は、その科学者が別のゾーンにいる時の当人とどう関係するのか。また、科学者に限らず人は科学の産出するこの「社会的現実」を個々のゾーンでどう使い分けるのか。こうした状況において「想定外」の出来事が起きたとしたら、どうなるのか。「良心の立入禁止区域」が至る所に出現するのではないか。
なるほどゾーンにも倫理はある。ただし、それはゾーン内での倫理である。そして、その内側での倫理の働きあいが、結果として3・11原発公害を発生させたといえないか。では、そうしたゾーンからの脱却を目指せば良いのか。だがことはそう簡単ではなさそうだ。ならば、逆にゾーンの内から内を開いていくのか。いずれであるにせよ、倫理(人の生き方)が問われる。本提題においては科学技術文明社会をゾーンとして捉え、そこでの倫理のあり方を歴史を踏まえながら考えてみたい。
(丹波 博紀)
【提題2】 欲望と想像力のゆくえ――シモーヌ・ヴェイユの思想をてがかりに
二〇一〇年九月に提題者がおこなったインタビューで辻井喬氏は、想像力をめぐる問題を的確な比喩を用いてこう述べている。「核兵器を創造する」ためには科学者の想像力が不可欠であるが、「核兵器を使用する」というのは想像力を失った人間でないとできない営みである、と。
想像力とは「イメージする力」である。そしてイメージとは、過去の記憶が現在に活き活きと思い出され、現在の直観を強め、未来への期待が思い描かれることである。このイメージを喪失してしまうとき、生息してはいても、わたしたちは自らの「生の創造」の担い手ではなくなってしまう。この「リアリティの欠如」は堪え難く、失った想像力に代わって「想像力のまがい物」がその埋め合わせをしようとする。この有り様は、たとえば、想像力が極端に欠如した時代に新興宗教が台頭し、テーマパークが増設されるといった現象を思い浮かべれば足りるであろう。
他方で、欲望はわたしたちの「生の創造」の原動力である。それゆえ欲望は、想像力の開花を促進するはずである。だがまさしくこの欲望こそがわたしたちから想像力を剥奪する最たるものとなる。別の言い方をするならば、わたしたち自身からわたしたち自身を剥奪するという自己矛盾を可能にしてしまう。プラトンが述べるように、本来、わたしたちの欲望はすべて「善への欲望」である。すなわち欲望は、自己自身という「有限」ではなく、世界と他者という「無限」へと向かうはずである。だがこの欲望は、科学技術の進歩という眩暈の直中で、いともたやすく有限のうちに無限を追求するという「欲望の転倒した体制」に陥ってしまうのである。
高度経済成長という時代背景のもと、被爆国であることがむしろ逆手にとられ、推し進められてきた原子力発電をめぐる問題や、毒だとわかっていて海や河に有機水銀を流すことを可能とさせてしまう環境破壊をめぐる問題は、この欲望と想像力の問題に帰着しうる。
本提題では、古代ギリシア思想のうちに、科学を技術から切り離し、純粋科学をもって想像力が十全に花開く場を見出したシモーヌ・ヴェイユの思索を訪ね、「われイメージする、ゆえにわれあり」と言いうる、イメージによる自由の再構築の可能性を浮き彫りにしてみたい。その際、科学をめぐる映像作品における様々なショットを「具体的なもの」と見立て、抽象と具体、個と普遍の往還に留意しつつ、思想が生きられ感じられ場を再現してみたい。
(今村 純子)
【提題3】 自然的な様相における人間の営みとは──津波・原発の歴史を振り返ってみる
全体の主題「科学技術文明史と倫理」をめぐって、ここでは、出来るだけより基本的な根のような形態についてとらえ考えてみたい。その形態をめぐる問題は、いま現在、事件としての日本の東北における津波・原発に結集して現れている。そこには人間の、自然との関係、社会のあり方、歴史認識などに関わる倫理的な要請が、根本的に発生している、と考えている。
倫理を、人間の生き方──生や行動や営為の、仕方・捉え方・営み方だと、考えておく。すると、倫理への問いは、結局はいまの人間──いま・生きている自分たちに、収束していく。もちろん、その問いの結果は、重要なことに他物・後代にまで広く深く繋がる。だから、そこには、大きな責任が含まれている。けれども、その問い自体は、結局、動植鉱物や死者たちに向かわず、いまの人間にこそ向かう。その意味で、そこに担われる内容はとても大きい。では、だとすると、その「人間」(いま・生きている自分たち)の「生き方」(生や行動や営為)は、さらに具体的にはどのような形態となって問いを生じているのか。そこに踏み込むとき、現在、要するに三つの問題が生じている、と思う。
第一に、人間は、自分として誰かとして人々として、また様々な何か誰かとの関係・交流によって、いま生きている。生きている限り、その関係・交流には、当の自分における、身心や物事の形成があり解体がある。生きていることには、文字どおり生命(いのち)が孕まれている。しかも、そこにはまた歴史がある。すると、どのような生命をめぐる形態史があるのだろうか。それは原発・津波にどう関連するのか。
第二に、歴史を振り返ると、とくに一九世紀半ば以後、人間において「社会」が形成され、またそこに生きる人間相互の格差、人口の増化が発生し始めた。そこにまさに「科学技術」「文明」が結びつく。このことは一体何なのだろうか。近代日本では、それは最初は、「国家」的課題だったようだが、さらに「宣伝・広告」となる。ただ、これは実は「社会」さらに「国際」、また「自然」の問題に繋がる。近代日本史において、これらの課題はどう解決されたのか。されなかったのではないか。
第三に、二〇世紀、人間の人為的生活形態、社会的国家的組織が形成され続けるが、世紀後半・世紀末からは、とくに「人間」における(1)国家枠を越えるインターネット・交通による国際化・地球化と、(2)エネルギー・力の所有・専有が結びついて発達する。原発はこれを支えている。と同時に、(3)自然における生物多様性のさらなる解体と環境の変容・破壊。これらは一体どういうことで今後どうあればいいのか。結局、人間が、グローバル化に関与しつつ、自身の、可能性・完全性・不完全性・偶然性を知り、形而上学をもいだき、自然的宇宙とも地球環境とも結びついた倫理・哲学を循環型生活において再発見すべきなのではないか。地震・津波・原発の事件は、そのことを人間に教えている。
(黒住 真)
【提題4】 学問にとって未来とは何か
学問は、正義と森羅万象に対する愛によって、平和にして豊饒な人類社会の実現を目指す知的な営みであり、そのような営みをなすコスモポリタンのコミュニティーである。学問の示す未来は希望と変化可能に充ちている。端的に学問は人類の幸福を目指す理性的な営為である。子どもや若者に学問への誘いを語ろうとすれば、このようなメッセージになるはずだ。
現にマイケル・ポラニー(*1)は、純粋な学問の精神は、正義と理性に対する信念に基づいており、世界が学問(科学)を必要とするのは「何よりも善き生活の範例」だからだと言った。科学のコミュニティーは、一定の信念への忠誠と権威、異論の調停、個々人の自由および自発性と協同の目的との調和を保証しているのであり、たとえドイツの科学者であろうが、日本の科学者であろうが、その態度を共有している。科学社会は、理想的な、あるいは自由な社会組織の範例なのだ。
すでに半世紀以上前、まさにそのような科学を夢見た身には、大学の片隅でひそかに暮らせたらという謙譲な思いと、貧困と不正のない社会の構築への寄与という熱い思いは同居していた。ポラニーは、第二次世界大戦後の情況において、破壊的懐疑主義が新たな情熱的な社会的良心と結びついた、すなわち「人間精神に対する完全な不信が過剰な道徳的要求と結びついた」状態に対して、科学の理想の擁護に固執しなければならないとした。
ポラニーの攻撃は共産主義に向けられたが、一九六八年、この破壊的懐疑と情熱的な社会的良心は、学生という層によって、共産主義も大学をも攻撃し、解体しようとした。特に日本においては、ファッショも軍部もやらなかった暴挙という印象さえ生まれたが、大学、学問、科学、技術、研究、研究費、講座制、国家、祖国、資本、精神労働、企業が様々な組み合わせ、からみあいとして問われた。なかんずく学生不在の大学とポラニー的科学共同体の不在が問われたのである。
しかし、ハンナ・アーレント(*2)は、一七世紀に始まった科学組織を指して、「全ての歴史の中で最も潜在能力のある権力発生集団の一つとなっている」とした。自然征服のために自分たちの道徳的標準と道徳的通念を発展させてきた組織は、自らの活動のため、時計に代表される技術を開発し、しかもその結果には無関心で責任をとらない。科学共同体は人間関係の網の目の中へとは活動しないのだ。
一九九〇年代、二一世紀冒頭の9・11、そして3・11を経た現在、ほとんどの学問がまきこまれた「科学する」倫理に改めてまともに向き合う必要がある。
*1「純粋科学の社会的メッセージ」(一九四五年)、『自由の論理』、長尾史郎訳、ハーベスト社、一九八八年
*2『人間の条件』(一九五八年)、志水速雄訳、ちくま学芸文庫、一九九四年
(最首 悟)
〇 日時:
2012年10月12日(金)
18時30分〜20時30分
〇 場所:
日本女子大学(目白キャンパス)
新泉山館・大会議室(日本倫理学会・第三会場)
〇 参加について:
★どなたでも参加可能です。申し込み手続きは不要です。
(受付にて「日本倫理学会大会報告集」を500円で購入できます)。
〇 日本倫理学会第62回大会について:
〇 ワークショップお問い合わせ先:
〇 関連企画:「現代倫理学研究会」(6/9)でのセッション&顔合わせ
・ 日時:2012年6月9日(土) 14時から19時まで
・ 場所:専修大学神田校舎 7号館・8階782教室
・ 参加費:なし(どなたでも参加できます)
・ 報告:
★第一部 報告:宮内寿子「ケアの倫理の陥穽」(仮題)
★第二部 セッション「科学技術文明史と倫理」(今村純子・丹波博紀が話題提供)
|