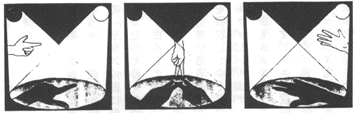 |
||||||||||||
|
リカーシヴな私
「半生(はんなま)の思想」(河合ブックレット・1991)からの抜粋
(前略)
大事なことは、知ることは未知との遭遇を増やすことであり、そのことを単純に自慢することはできないということです。オレはこんなに知っているということは、私的所有の問題とからんで、自慢することはできる、非常に子どもっぽいことにしても(そういう教師や教授がゴマンといます)。しかし、私は知らないことをこんなに沢山抱えているのだということについては、そう自慢することはできません。むしろ知の追求が未知の増大を招くことから、新たな世界認識の態度をみちびきだして、それに基づいて知の追求を放棄する道が開けないこともない。パスカルは最後まで数学を捨てなかったといわれるけれど、おおむねこの線にそった生き方をしたと思える。
日本にもそういう人はいろいろいるでしょうね。京大の学長をつとめた狩野亮吉などはどうでしょうか。安藤昌益を発掘した人です。
世界の大枠を設定しての出発と、世界は人間にとって究極的に認識されないという不可知的立場を提出したのですが、どちらにしてもこの「私」が大問題です。「私を知る」、すなわち私を対象化する、言い換えると、私を私の目の前に据えるということは、非常に古くて、そして新しい、世界の秩序の要の問題です。「私」を対象化すると「私の私」が登場してくる。この「私」についての無限系列は西欧の専売特許というわけでなく、心学の石田梅岩なども言っているようです。理屈として私は私からはみ出る、自己とは何かを問うと自己は最後まで残る、というようなことを考えた石田梅岩は京都の呉服屋の番頭さんだった人です。番頭さんをやめて石門心学を開くめずらしい人で、考えも特異、「自己とは不解決」の向こうに絶対を創定したりしないわけです。ふつうは自己が自己を呼ぶ無限系列に始末をつけるには、「無」か「神」を呼び込む、あるいは要請するのです。
要請しないとどうなりますか。反省的に私に向う他はなく、そのとき、私の無限系列は結局は「私は私である」ことにすぎないということになります。私という言葉を発したときに、すでにそこに含意されていた私なるモノから私は一歩も踏み出していないという意味です。私は私という閉鎖領域の中をグルグルと回っている。循環している。
「私とはリカーシヴな私である」。リカーシヴとは、循環する、円環的である、回帰的である、というような意味ですが、要するにニワトリが先かタマゴが先かということです。私というモノがさしあたり、精神と肉体からできていて、それらが独立していようと主従関係にあろうと、共約(カップリング)していようと、どうでもよいのだけど、「私は私である」という循環は、私がいやおうなく自律体であることを示していると考えられる。そこから出発して私の精神は自律的である。肉体が自律的である、精神と肉体という共約体が自律的であるということは論じていいのですが、根本はこの私が自律体でしか有り得ないということなのです。
ただ、急に私は自律体であるといわれても私たちはキョトンとするか、うろたえてしまう。その事情は西欧でも東洋でも同じだと思われます。大きく言って私たちは自律体であることの確証を得ようとしたり、自律体であることの不安を免れようとしてきた、そういうふうに世界を構築してきたと言えるだろうと思います。
たとえば競争。張り合うことで自律性を確認したり誇ったりしようとする。学問的営為はその典型と言える。
たとえば服従。服従は問題回避として、とても気持ちのよいモノである。服従とは自律体の規模を大きくして行くことで、家族、集団、国家、神とか天というような自律体への従属体として自己規定することは人間の真の快楽だともいえるのです。私たちには、「私が私である」ことは競合と服従の釣合いの問題であったともいえそうです。
しかし、競合にしても服従にしても、この「私」が前提されていなければ、そもそも起こらぬことです。「ニワトリが先かタマゴが先か?」は、生物の自律性を表現しているところに意味があり、そして次に大事なのは、たぶん「私が私である」ことを、この問いが取り込んでいる、つまり自己をめぐるリカーシヴ性は生物のリカーシヴ性に包摂されるだろうということです。たぶん、と留保するのは、精神の自律性の間題があるからです。とは言っても、精神の自律性もまた生物になぞらえて論じられることが多いのですが。
生物の自律性はまずは「生きている」ということで、「生きている」とはどのようにしてもどこかでポンと飛び出してくるシステムの自動稼働状態を意味します。構造と機能が共約しているので、どのようにシンプル(?)な「生きている状態」を考えても、「生きていない状態」から連続的に生起することができない。「ニワトリが先かタマゴが先か?」は、このポンと飛んだかぎりでの「生きている」ことの連続性を言い表しています。生命の設計図を描くとはどういうことか。目的があって、どのようなことに使うか機能を定めて、構造が決定される。その構造にしたがって部品の設計をしてゆく。このように設計図を描くには膨大な前提が必要です。厄介なのは、設計図というモノそのものの問題で、紙も鉛筆も定規もなくて、この世に設計図なるモノが一枚もないとき、設計図なる考えはどこから来るのだろう。万能者の存在を導入したくなるのはヤマヤマで、最初の一枚とか、最初の一撃もヴァリェーションに過ぎません。それから、量が質に転化するという言い方は、生命にとってあまりにも粗雑すぎます。
頭がクシャクシャするからね、ポンと飛んだあとの循環的保存、発展に移ると、これは完全な連続性にあります。細砲分裂というのは、ふつう、親細胞が二つの娘細胞に分かれるのだけれど、親細砲が連続的に娘細胞に移行したのは明らかです。じやあ、剛構造をもつ器官の成長はどうだろうか。貝殻とか歯のようにホウロウ質という固い物質に蔽われていて、それが大きくなって行く。サザエの殻は巻いていますが、子どものときと大人で巻数が変わるわけでなく、相似的に大きくなってゆくのです。機能としては、一瞬の体みもなく、複雑かつ剛性の層状構造を保ったまま、成長してゆく。どうやって?
ウニの場合はもっと衝撃的です。プルテウスという東京タワーみたいな幼生がいて、生きて活動しているうちに、ウニ原基なるモノが出現してプルテウスと共存しながら、次第にプルテウスを吸収してゆく。ついにはプルテウスがなくなって1ミリくらいのウニが誕生する。このメタモルフォーシスはサナギやカエルにくらべて、想像を絶するものがありませんか?そりやあ、サナギもカエルもすごいけれど、サナギは休止状態が間に入るし、オクマジャクシの口はカエルの口です。ウニの変態の場合はまったく休まないし、プルテウスの口とウニの口はまったく関係ないのです。連続が保障されて、なおかつ個体性の連続があいまいな例です。
センベイを少しずつ齧ってゆくような明晰化、すなわち未知の減少の立場と、知の拡大こそが未知を出現させるという立場に加えて、切断的に出現する閉鎖領域での循環の連続性を出しましたが、もう一つ考えてもらいたいのは、不確定性原理とはちがう、認識の限界、説明不能性というようなことです。ゲリッケの「色彩の影」(1672)という現象があります。
離した二つのスポットライトでテーブルの同一場所を照らします。一方はふつうの自色光源で、一方は赤にします。光の領域は二つあって、それぞれのスポットの光のみの領域と二つのスポットが交錯している領域とがありますね(図1)。赤のスポットの光のみの領域に手を入れるとテーブルの上の二つの光が重なっている場所にできる手の影は青緑になります。白色の方に手を入れるとその影はエンジ色になる。青緑になるなんて信じられません。
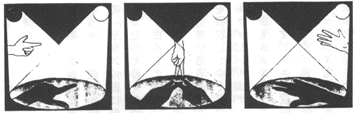 |
||||||||||||
|
実際にスペクトルを測っても青や緑のスペクトルが優勢であるわけではないのです。これは私と君がリンゴを見て、たしかに赤いと頷き合うとき、しかしどんな赤なのだ、赤といってもいろいろあるという問題とレベルがちがいます。お互いに赤だと認識するにもかかわらず、赤であるならば存在するはずの波長のスペクトルがないということで、観察とか、客観の意味が保てなくなってしまう事態です。
じっと見ていると反転が起こってしまうシュレーダーの階段など(図2)、考えると、自分は何を見ているのかわからない怖さを生じさせます。以上お話してきたことは、勉強や学問の上での、目的性や因果性や確からしさの危うさだというふうに言えます。
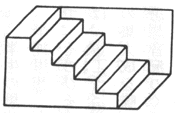
(後略)