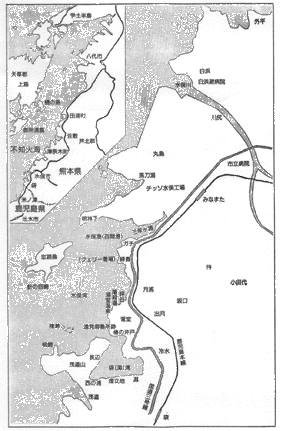
湯堂という漁村の生活(1)
熊本県水俣市袋湯堂。大正元(1912)年まで芦北郡水俣村大字袋字湯堂とよばれた小さな漁村のことについて述べてみたい。
鹿児島本線水俣駅は、特急がとまる。ここで普通列車にのりかえ鹿児島方面に向かうと、一つ目が袋駅(5.8キロ)である。その次の米ノ津駅はもう鹿児島県に属している。袋駅から国道三号線を水俣のほうへ約1キロメートルもどったところが袋の集落の中心部で、江戸時代はここに袋口御番所があった。このあたりの様子を伝える18世紀なかばの文献には、「袋村あり、今家数15軒ほど。此村に御番所あり」(鳥居文書)とあって、集落の大きさがうかがわれる。
袋という地名は、巾着のようなかたちをした袋湾に由来している。不知火海というその主部は琵琶湖ぐらいの大きさの典型的な内海がまたいくつも二重湾をつくっている。田浦湾や佐敷湾とならんで水俣湾も代表的な二重湾である。ところがこの水俣湾には他にはみられない特徴がある。それはなんと湾の内に見事な三重湾を抱えていることであって、湾口わずか110メートル、奥行は広々としたこの三重湾を袋湾という。袋湾のいちばん奥、袋の底にあたる部分が袋の集落である。
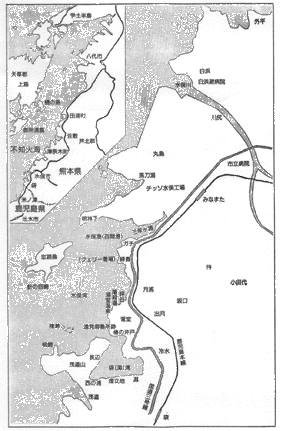
穏やかな海に面して
外洋を見なれた者にとっては、不知火海はまるで湖のような感じがする。そのように穏やかな内海の三重湾というのだから、袋湾は鏡のようだといわれるのも不思議はない。台風の季節の避難港としての機能はもとより、平常も運搬船が寄ってきた。それゆえここにも御番所がもうけられた。陸の袋口御番所に対して、海のほうは遠見の御番所とよばれる。水俣湾から袋湾に入ろうとするとき、狭い湾口の左手に御番所があった。湾に入ると御番所跡と同じ側に見えてくるのが湯堂の漁村である。海辺から60メートルぐらいの落差がある国道三号線までの狭い急な斜面に集落は展開している。
湯堂部落の対岸は、それはすばらしい黒松がびっしり生えた茂道山てあった。御番所跡の背後も、うっそうとした照葉樹林の山である。
細川藩の時代(1632−1871年)、水俣の惣庄屋(代官)は深水家で、そのはじまりは寛永11(1634))年であるが、初代頼氏(水俣吉左エ門)は強引に茂道山に松を密植した。もともと島津藩に対峙する最前線基地として、茂道山に松を植え立てるなら強力な要害になると予想され、その用意もたびたび試みられたのだが、なにしろ大がかりなのでできなかった。それを、
−−吉左エ門頼氏せき立て騎馬にて槍を持たせ罷り出で植させ申し候。(深水家系譜)−−
という次第で、おそらく藩からの強力な命令のもとに、大人数を繰り出し、非常時態勢のようにして植えたのだろう。吉左エ門が惣庄屋になったときすぐにこの重公役を課したとすると、系譜の二代頼秋の項で次のように述べられている寛文7(1667)年は、35年後のことになり、松は成木になっている。
−−茂道山松いよいよ盛長に相ひ成り、江戸御屋形御用の由にて、先の植立て分二万本伐り申し候之共、跡目立ち申さず、茂り居り申し候事。−−
茂道松は材質がよく、造船材としても最優秀であると人口に膾炙したため、細川家も深い関心をもち、水俣代官深水家は代々茂道松の管理と造林に力をそそいだという。寛永のころ植えられ、最近まで(といっても昭和10年代のことだが)残ったと思われる松は、茂道山の大山神社の前にある2本の大木で、大人が6人手をつないで抱きまわすくらいだった。直径約3メートルの神韻縹渺とした老松だったと、老人の記憶に残っている。
さざなみ一つ立たない入江に色濃く影を落とした松は魚付林となって、袋湾はイワシのような回遊魚の休息(と信じられている)と産卵の絶好の場であった。その上、湾の入口に真水の大湧出地があり、春にはエビナ(ボラの子)が押し寄せ、鮎子が群らがっていた。国士地理院の5万分ノ1地図では、袋湾は湯湾となっている。背後の矢筈岳から冷水(ひやすじ)を通った地下水の湧出の特徴をとらえた名称と思われるが、湯堂という地名とともに湧泉源の存在を示唆しているとも考えられる。近年実際に温泉の掘削に成功し、湯堂温泉になっている。
その昔、人は天草からもやって来た
入り江を少し入った、御番所の近くの、舟をあがったすぐの所に、大きな共同井戸が2つあった。地元の人たちは真四角なカワという。椿の木の井戸ともいう。
−−井戸の上の崖から、樹齢も定かならぬ椿の古樹が、うち重なりながら、洗場や、その前の広場をおおっていた。・・・井戸も椿も、おのれの歳月のみならず、この村のよわいを語っていた。(石牟礼道子『苦海浄土』)−−
カワは水タゴ(捕)に水を汲みいれたり、洗濯をする女たちでにぎわっているばかりではなかった。イワシ桶を洗い、網洗いを競う男たちで修羅場めいたりもした。たぶんこの広々とした四角なカワの歴史は古い。そしておそらく人の住みついたのも古いだろう。
しかし湯堂部落の歴史は意外とたどれない。いま神奈川県に住んでいる大村トミエさん(昭和8年生まれ)は、昭和19(1944)年に死んだおじいさんの坂本徳次さん(明治5<1872>年生まれ)から、昔ばなしをよくしてもらったが、それによると、徳次さんの父親は天草から渡ってきて、遠見のソト(トミエさんは御番所のことをトウミのソトといい、子どものときからどんな漢字を書くのか不思議に思っている)の下働きに入ったという。名前はクルマツといい、留というような字に松だった。久留松ですかと尋ねたら、いやあ、留というような漢宇一字だったという答えであった。徳次さんがおそい子で、クルマツさんが10代の後半に海を渡ってきたにしても、クルマツさんが湯堂に居ついたのは、一番早くて天保の10(1839)年くらいだろう。
荒木ルイさん(明治43<1910>年生まれ)によれば、おじいさんが天草御所浦島の唐木崎から慶応元(1865)年ごろやってきたという。
鶴見和子による前鳥日与喜さん(昭和7〈<1932>年生まれ)の聞き取り(色川大吉編『水俣の啓示』上巻)では、湯堂は、隣りの月ノ浦が本部落で、はじめは月ノ浦湯堂とよばれていた。月ノ浦の前島家は、御番所の下働きをしていたが、その二、三男が分家して湯堂に居をかまえたのが湯堂部落のはじまりである。明治初年には、月ノ浦からの前島、坂本、遠くはなれた芦北の田ノ浦からの岩坂の3軒ぐらいが土着で、あとは天草からの移住者だった。
月ノ浦からきた坂本家の分家筋の坂本嘉吉さん(明治29<1896>年生まれ)の記憶では、嘉吉さんの父親が生まれた明治10(1877)年のころは、湯堂は7、8軒の集落だった。もともと5、6軒が元祖で、明治40(1907)年ころには20軒から25軒になっていたが、増えたのはみんな天草からの人たちだった(岡本達明編『近代民衆の記録7・漁民』のなかの坂本嘉吉聞き書)。
明治時代、25軒ほどの貧しい漁村
浜にはポツンポツンと家があった。浜といっても山がすぐせまっている。天草からやってきた人たちは、山を切りくずして石垣を築いて家を建てた。海に張り出したかっこうになっているので、潮が満ちれば隣の家に行けなかった。
すこしまとめてみると、湯堂は天保2(1840)年に肥後名所の一つに選ばれ、文人墨客の来遊が多かった(『熊本県百科事典』)とはいうものの、住む人は少なく、隣部落の月ノ浦の「わかされ」(分家)と海上24キロ難れた芦北郡の田ノ浦から、漁の前進基地としての移住者をたして3、4軒と、天草流れの家が2、3軒のみの状態で明治をむかえた。それから明治の終り近くまでの40年間に、天草からの移住がポツポツあって25軒ぐらいの集落になった、ということになる。
風光明媚な反面、急な斜面の怖ろしいような孟宗竹の山や、猫が走りこもうと思っても走りこめないような薮山を切りひらくのはたいへんなことだった。周辺の既存部落にとって湯堂は住むには魅力がなかった。住むための土地の切り開きなら、まだ相対的に容易な地所があった。そのため湯堂は、<天草もん>にむかってひらかれた土地となった。主に御所浦島から、それぞれ事情あって不知火海を渡ってきた人たちは、湯堂の海辺にしがみつくようにして掘立小屋を建てた。
明治42年、水俣肥料工場完成
ちょうどこのころ、明治42(1909)年、日本窒素肥料株式会社の水俣肥料工場が完成した。資本金100万円でスタートしたこの会社は、7年後の大正5(1916)年には資本金を10倍に増資し、大正7(1918)年に新水俣工場を完成させ、同時に水俣湾百間港に廃水の無処理放流をはじめた。
この新工場建設によって、湯堂への天草からの流入は一拳に増えることになる。会社目当てに縁者をたより、あるいは直接会社へ入ろうとしなくても、新興の息吹きのなかに、新たな生活の可能性を感じとって、人びとは天草からやってきた。大正7年から昭和初年の7、8年間に、湯堂の戸数は7、80軒になったという。どこもそこも掘立小屋で、湯堂の背後の丘の坂口に入った人たちのなかには、櫨と櫨の間に木を渡し、地面を掘り下げて掛小屋にする人もいた。竪穴式住居の智恵である。掘立小屋の入口は、ヘゴ(萱)のスダレでおおった。このことから<スダレもん>という呼称がおこった。
天草の人たちが住みつくことがてきたのは、海辺では湯堂のほかに、茂道、月ノ浦、出月、丸島、そして山ん中の、小田代、侍、外平(ほかびら)、であった。山間部の苦労はまたひとしおで、「天草ン人たちはねえ。田舎も田舎、山ン中も山ン中、もう水も二山越えつ担い上げつ、使い水ば汲みよられましたっですばい」というような、水俣の町なかの老女の証言が、『近代民衆の記録』にみられる。この記録のなかには天草流れの人たちに対するあけすけな差別の言葉が多くならんでいるが、その一つを引用すると、
−−天草は島やッで、縞ン着物ち、言うとですたい。水俣は島じャなかで、紺の着物ち、言うとですたい。「ありャ、縞ン紋じャが」「縞ン布じャが」ち、言いよりましたっばい。誰っでン、あんまり好きませんじゃったな。−−
というようである。もともと士農工商漁民と位置づけされた漁民のなかでも、漂海の漁民は賤民扱いをされていた。
天草流れの人たちはそのようにみなされた。言葉が通じないことからはじまって、そもそも<精神の悪>く、何かおこれば、天草者のしわざであるにきまっていた。湯堂は、そのように差別された天草流れの人たちの比率がもっとも多い底辺漁村社会であった。
その当時、湾には魚が群れていた
湯堂部落が25軒ぐらいであったころ、すなわち日窒工場が稼働しはじめた明治末期、袋湾や水俣湾は魚が無尽蔵にいるように思われた。湯堂はことに多く、船から糞をすると、二尺ぐらいのチヌ(黒鯛)が、海底が見通せないくらいおり重なって、何千匹と集まり、大口をあけてゴポゴポと糞を含ったという。坂本嘉吉さんの13歳ごろの記憶である。現在が悲惨であるほど、思い出はふくらんでいく。それにしてもチヌは多かった。
このころ、いわし地引網の網元は、月ノ浦から来た坂本重吉と、田ノ浦から来た岩坂若松の二軒であった。なんといっても、マイワシ、カタクチイワシのイリコ(煮千)製造が主漁業で、天日干しでめるため入梅を避けるのと、冬期のシロゴ漁(シラス千し)をのぞけば、周年漁であった。地引網の網代は、袋湾のなかは、奥から潟(がた)、西ノ浦、長辺(ながへた)、湯堂下の4カ所、水俣湾に出ると、三年ケ浦の緑鼻(みどりばな)、フェリー着場(昭和60年、緑鼻に移った)のガチ、そして日窒水俣工場の廃水がもろにぶつかる明神下の三カ所が、入会い的な網代で操業できた。外海(不知火海)や水俣湾が時化ても、袋湾は大丈夫だった。
網は小地引網といわれる小型のものだったが、それでも片方の曳手に8人を要し、船頭船には漕手1人と、網のつり合いの指示役(弁ざし、船頭)1人が乗るので、合計18人ぐらいが網一統に必要だった。戸数は25軒、青年とよばれる年頃の男女は合せて15人しかいなかった。だから男も女も漁に出た。水俣湾の網代の朝網などには、宵の内から男も女も船にのって網代に行き、船で寝た。朝3時にはイワシが押し寄せてくる。そのような生活が一年中続いた。
働ける者全てが漁に出るわけにはいかない。イリコ製造用のマキ集めが重労働だったし、農作業もある。ただし、あとで述ベるが、田や畑がほとんどないことが、湯堂の貧困の限定的要因であった。
地引網の他に魚(いお)網(底引綱)があった。袋湾の奥の潟や、水俣湾の明神下でひいた。後年、何メートルものヘドロで埋めつくされる明神下は、まだ砂と小石の清浄な海底だった。魚綱は、ポラ、エノイオ(エイ)、コノシロ、カレイ、クロイオ(メジナ)、タチウオなどが獲れた。
それでも苦しい漁師の暮し
湯堂の漁の特徴は、湾口のせまさを利用したボラ漁である。満ち潮でボラがのりこんでくると、湾口に二間ごとに竹棒をたて、それへ網を張る。潮がひきはじめてボラが湾口に向かうと綱にぶつかり反転して湾奥に逃げる。潮が十分引いたとき、投げ網てボラをとる。何十貫と獲れる。ときに何百貫と渡れたこともあった。この日は、人でにぎわい、袋の駐在さんが来て整理したこともあったという。この漁法は江切(えきり)網あるいは建干(たてぼし)網という。天草から来た人たちに、湯堂には、網子の仕事があった。一本釣りも、せいぜい出かけても恋路(こき)島ぐらいの範囲で漁ができた。春の鯛釣りが本命で、チヌ、アジ、セノイオ(イシモチ、メバル、カサゴなど)、キスゴ(キス)、イトヨリなど、夜明けの海に魚はいた。
それで、魚がいて漁ができれば、平穂に碁せたのか。それがそうはいかなかった。御所浦島嵐口(あらくち)から湯堂にやってきた舟大工の荒木幾松さんによれば(『近代民衆の記録』)、大正8(1918)年ごろ湯堂には小船が20艘(ぱい)ぐらいいたが、なんともいえぬボロ船だったという。船釘は12、3年もつのだが、湯堂の船は釘がみんな切れて(くさって)、ボロ布を噛ませて使っていた。ほんとうのボロ船だった。彼によれば、湯堂の漁師の暮しはきつく、一本釣りはよほど獲らないと金にならなかったという。切り貼り切り貼りしてゆくような船の修繕に銭を払ってくれるのは、坂本嘉吉さんの本家だけだったそうだ。
どんなに魚がいても、冷蔵設備がなく、販売圏がかぎられ、需要が一定の枠内におさまり、しかも魚価が買い手市場であれば、漁師は楽になりようがない。漁網は、綿網にかわりつつあったが、綿網は高価で、耐久性がなかった。網元こそは借銭だらけだった。1カ月か2カ月ごとの網漁の計算(締め)によって、網子への報酬がきまるが、ここで現金が動くわけではない。網子はすでに前借りがかさんでいる。網元は前貸しする器量がなければ店をはってゆくことはできない。そして湯堂の貧乏は土地のないことだった。
工場の、職工募集は”衝撃的朗報”
湯堂で水田をもっていたのは2軒だけだった。あと何人かが畑をもっていた。田をもっていた2軒のうちの1軒は、坂本嘉吉さんの本家である。嘉吉さんの叔父さんにあたる福次郎さんの子ども、つまり嘉吉さんにとって従兄弟である坂本武義さんのところに、その何割かが伝わったと思われるが、武義さんのところには、水田が2反5畝、畑が4反、山林が3町あった。福次郎さんは明治17(1884)年生まれの、湯堂を代表する秀でた漁師で、昭和43(1968)年に84歳で没したとき、湯堂の一つの時代が終ったといわれた。
戦前、昭和年代に入ってから、米の収量は反あたり2石(300キログラム)ぐらいであり、一人平均の消費量は、約1石だった。武義さんのところの水田は、そうすると、全部食べてしまったとしても、平均消費量でいえば五人の糊口しか、しのげないことになる。決定的に米とワラが足らなかった。湯堂の田と畑は、兄弟や子ども縁者が借りるのがせいいっぱいで、他所から来た人たちは、出月や坂口のほうまで借りに行かねばならなかった。借りられるならまだよい。借りられなければ血まなこになる。そうすると開墾していない人の土地を無断て耕したり、道のぐるりの畑を割った残りのほんの少しのところをせせくるように作る。それをみて「やっぱり天草もんは汚なかです。心の」というような風評が流れ固定することになるのだ。「ジョウジョウカライモ、イワシのシャー」(常々唐芋、鰯の菜)といわれたサツマイモも、湯堂では三度の食事に十分食べるというわけにはいかなかった。
<湯堂ち所は、ほんなごて、貧乏村やったっばい>という述懐が、重いガスのように発生してくる生活環境にとって、日室水俣工場の操業及び職工募集は、衝撃的朗報であった。
そして、近代がはじまった
当初、水俣の町なかの人びと、および農民層は工場に反発し、工員は愚弄の対象であった(色川大吉「チッソの進出と水俣民衆史)。工場の労働条件は悪く、24時間二交替制の上、賃金は一般の人夫賃より低かった。まるで懲役人を使うようであったという。それゆえ工場は、生活に困った人間の行く所とみなされ、<会社勧進(乞食)>という蔑称も生まれた。
しかし天草流れの人たちにとっては、現金収入のある職場は大歓迎であった。苛酷な労働も、食えないよりはましだった。工場側も積極的に天草や鹿児島に足をのばして<人買い>につとめていた。湯堂から会社行きが出た。坂本嘉吉さんはそのころ父親と、海竜丸という十万斤積の運搬船で茂道山の官松材を佐世保に納めていたが、この事態について、次のように語っている。
−−新工場の出来てからが網子が居らんようになったったいな。湯堂の漁師の組は、若い連中はほとんど会社に入ってしもうたもね。そりや、会社が良かった。その頃は銭取り仕事は他になかったろうがな。今度(こんだ)、船方する者も居らんごつなってしもうたったい。長崎、佐世保まじゃ三人はどうしても要るもン。それで私共もう止めたっじゃった。(「天草漁民間書」)−−
その網子の穴を埋めに、そして会社に行くために、天草から湯堂に多くの人たちが渡ってきた。もちろん湯堂だけではない。会社のある町なかから離れた周辺部に、原始的な掘立小屋をつくって大勢の人が住みついた。原始と差別の上に近代がはじまったのである。
つづきは湯堂という漁村の生活(2)へ
| メール |